都道府県別年間雷日数
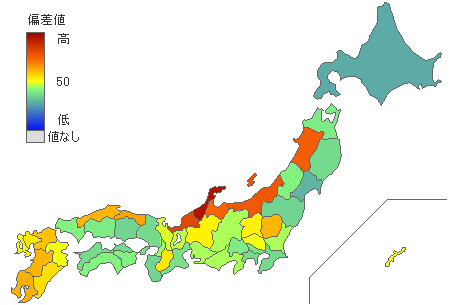
気象庁の平年値データから年間雷日数の都道府県別ランキング。ここでは県庁所在地の気象データを都道府県の値としている。なお、以下の県では県庁所在地に気象台がないため、別地点のデータを使っている。
埼玉県:熊谷市 東京都:千代田区 滋賀県:彦根市
気象庁では過去30年間のデータから平年値を出しており、ここでは1991年から2020年のデータによる平年値を比較している。
年間雷日数の全国平均は20.1日。これは各都道府県のデータを相加平均したもので、気象庁が発表したものではないので注意願いたい。
雷日数が最も多いのは石川県で45.1日(偏差値82.9)。2位は福井県で37.4日。3位以下は新潟県(34.7日)、秋田県(34.3日)、富山県(33.6日)の順。北陸各県が上位を占めているのは冬季の雷が原因だ。
日本海側の雷
北陸地方や新潟県、山形県庄内地方、秋田県などの日本海沿岸では、冬季に目立って多く発生することから冬季雷とも呼ばれる。冬季雷は夏期のものが積乱雲から地面に向かって放電するのに対し地面から積乱雲に向かって、上向きに放電する。落雷数こそ少ないものの発生のメカニズムから夏季の雷より数百倍のエネルギーを持つものが確認されるほか、一日中発雷することが多く雪やあられを伴うことが多い。また、はっきりとした落雷が無くても瞬間的な停電などの被害が出ることもある。海岸線から35km以上の内陸部では少ない。
また、冬季の雷には愛称があることが多く、「雪起こし」、「ブリ起こし」、「雪雷」などのような方言がみられる。特に、雪起こしが観測された場合は冬の始まりであると言い習わされる。
北陸を含む日本海側に続いて多いのは九州地方で、梅雨や夏の雨天の多さが影響していると思われる。
一方、最も雷日数が少ないのは北海道で9.2日(偏差値35.6)。これに宮城県(9.8日)、岡山県(12.6日)、福島県(12.6日)、和歌山県(12.7日)と続いている。
また、雷が多いと言われる群馬県の雷日数は21.8日で15位。偏差値も52.22で、とりたてて多いということはない。東京都や神奈川県など南関東の雷日数が少ないため、相対的に多く見えるのだろう。
他との相関では年間雨日数と高い相関になっていて、雨が降る日が多い地域ほど雷が多いことが分かる。また、北陸に本拠地を置く100満ボルト店舗数とも正の相関があるが、雷の多さと店名に関係があるのだろうか。
データ出典 気象庁 2020
□ 都道府県別年間雷日数
「並替」の右横の「北/南」「降順/昇順」をクリックすると並べ替え表示します。
| 順位 | 都道府県 | 雷日数 | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| 並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
| 1 | 石川県 | 45.1日 | 82.88 |
| 2 | 福井県 | 37.4日 | 72.75 |
| 3 | 新潟県 | 34.7日 | 69.20 |
| 4 | 秋田県 | 34.3日 | 68.67 |
| 5 | 富山県 | 33.6日 | 67.75 |
| 6 | 鳥取県 | 28.0日 | 60.38 |
| 7 | 鹿児島県 | 27.4日 | 59.59 |
| 8 | 島根県 | 26.6日 | 58.54 |
| 8 | 熊本県 | 26.6日 | 58.54 |
| 10 | 栃木県 | 26.5日 | 58.40 |
| 11 | 福岡県 | 25.5日 | 57.09 |
| 12 | 宮崎県 | 23.5日 | 54.46 |
| 13 | 奈良県 | 23.1日 | 53.93 |
| 13 | 佐賀県 | 23.1日 | 53.93 |
| 15 | 群馬県 | 21.8日 | 52.22 |
| 16 | 岐阜県 | 21.7日 | 52.09 |
| 17 | 長崎県 | 21.6日 | 51.95 |
| 18 | 沖縄県 | 20.4日 | 50.38 |
| 19 | 大分県 | 20.3日 | 50.24 |
| 20 | 埼玉県 | 20.2日 | 50.11 |
| 21 | 京都府 | 19.6日 | 49.32 |
| 22 | 滋賀県 | 18.9日 | 48.40 |
| 23 | 静岡県 | 18.1日 | 47.35 |
| 24 | 愛知県 | 18.0日 | 47.22 |
| 25 | 茨城県 | 17.9日 | 47.09 |
| 25 | 長野県 | 17.9日 | 47.09 |
| 27 | 大阪府 | 17.3日 | 46.30 |
| 28 | 高知県 | 16.2日 | 44.85 |
| 29 | 山口県 | 16.0日 | 44.58 |
| 30 | 山形県 | 15.9日 | 44.45 |
| 30 | 徳島県 | 15.9日 | 44.45 |
| 32 | 青森県 | 15.2日 | 43.53 |
| 33 | 広島県 | 15.1日 | 43.40 |
| 34 | 山梨県 | 14.8日 | 43.01 |
| 35 | 東京都 | 14.5日 | 42.61 |
| 36 | 三重県 | 14.3日 | 42.35 |
| 37 | 兵庫県 | 14.0日 | 41.95 |
| 38 | 神奈川県 | 13.8日 | 41.69 |
| 39 | 岩手県 | 13.6日 | 41.43 |
| 40 | 香川県 | 13.4日 | 41.16 |
| 40 | 愛媛県 | 13.4日 | 41.16 |
| 42 | 千葉県 | 13.3日 | 41.03 |
| 43 | 和歌山県 | 12.7日 | 40.24 |
| 44 | 福島県 | 12.6日 | 40.11 |
| 44 | 岡山県 | 12.6日 | 40.11 |
| 46 | 宮城県 | 9.8日 | 36.42 |
| 47 | 北海道 | 9.2日 | 35.63 |
| 全国 | 20.1日 |
□ 他との相関 相関とは?
- 赤字は本文内で言及したランキング
- [0.81] 年間雨日数 [ 2020年第一位 富山県 ]
- [0.60] 年間降水量 [ 2020年第一位 高知県 ]
- [0.58] 100満ボルト店舗数 [ 2011年第一位 福井県 ]
- [0.58] 生け花・茶道教室数 [ 2014年第一位 石川県 ]
- [0.56] ふりかけ消費量 [ 2018年第一位 山口県 ]
- [0.55] 2014年衆議院比例代表:自由民主党得票率 [ 2014年第一位 富山県 ]
- [0.54] 2016年参議院比例代表:自由民主党得票率 [ 2016年第一位 石川県 ]
- ・
・ - [-0.45] 甲子園2000年代勝率 [ 2009年第一位 神奈川県 ]
- [-0.47] 救急出動件数 [ 2013年第一位 大阪府 ]
- [-0.49] 不動産賃貸・管理業軒数 [ 2014年第一位 東京都 ]
- [-0.52] 中学生長時間テレビ視聴率 [ 2015年第一位 京都府 ]
- [-0.54] 中学生長時間ゲームプレイ率 [ 2015年第一位 和歌山県 ]
- [-0.55] 年間晴れ日数 [ 2020年第一位 宮崎県 ]
- [-0.55] 中学生長時間ネット利用率 [ 2015年第一位 神奈川県 ]
- 全ての相関を見る
□ 気候に関するその他の記事
- 2023-04-24
- 2023-04-18
- 2023-04-18
- 2023-04-17
- 2023-04-17
- 2023-04-14
- 2023-04-13
- 2023-04-11
- 2023-04-11
- 2023-04-11
- 2023-04-11
- 2023-04-10
- 2023-04-10
- 2023-04-10
- 2023-04-10
- 2020-08-26
□ 雷日数の分布 (変動係数 0.3777)
□ この記事を見た人はこちらも見ています
□ コメント
イマイ 2018/08/27
やはり日本海側が多いが、夏は北関東(栃木など)が多い。