都道府県別高齢夫婦世帯の相対的貧困率
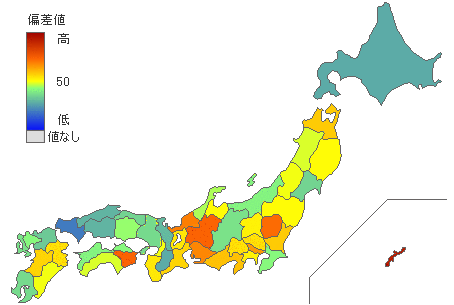
総務省統計局の住宅・土地統計調査から高齢世帯の相対的貧困率のランキング。同調査では各都道府県の世帯数を世帯年収別に集計しており、そこから高齢夫婦世帯の貧困率を独自に計算した。
高齢夫婦世帯 夫65歳以上,妻60歳以上の夫婦1組のみの一般世帯
相対的貧困率とは国民を所得順に並べて、真ん中の順位(中位数)の人の半分以下しか所得がない人(貧困層)の比率を意味する。 つまり、中位の人の年収が500万円だとしたら、250万円以下の所得層がどれだけいるかということだ。
相対的貧困世帯率計算の元になる中位数(中央値)は全国平均ではなく各都道府県ごとに別々に算出している。つまり、その県の年収が低くても、貧富の差が小さければ相対的貧困率が低くなるし、年収が高くても、貧富の差が大きければ相対的貧困率が高くなるので注意願いたい。
高齢夫婦世帯の相対的貧困率の全国平均は20.27%。相対的貧困率が最も高いのは沖縄県で30.74%(偏差値80.6)。2位は徳島県で26.48%。3位以下は岐阜県(26.25%)、栃木県(26.17%)、福井県(25.27%)の順。一方、最も相対的貧困率が低いのは山口県で13.83%(偏差値29.6)。これに北海道(15.61%)、奈良県(15.66%)、広島県(16.19%)、島根県(16.24%)と続いている。
他との相関を見たが、関連性を思わせる相関は見当たらなかった。
データ出典 住宅・土地統計調査 2018
□ 都道府県別高齢夫婦世帯の相対的貧困率
「並替」の右横の「北/南」「降順/昇順」をクリックすると並べ替え表示します。
| 順位 | 都道府県 | 相対的貧困率 | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| 並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
| 1 | 沖縄県 | 30.74% | 80.62 |
| 2 | 徳島県 | 26.48% | 67.77 |
| 3 | 岐阜県 | 26.25% | 67.08 |
| 4 | 栃木県 | 26.17% | 66.84 |
| 5 | 福井県 | 25.27% | 64.13 |
| 6 | 愛知県 | 25.02% | 63.37 |
| 7 | 東京都 | 24.28% | 61.14 |
| 8 | 静岡県 | 23.02% | 57.34 |
| 9 | 青森県 | 22.66% | 56.26 |
| 10 | 茨城県 | 22.64% | 56.20 |
| 11 | 熊本県 | 22.38% | 55.41 |
| 12 | 三重県 | 22.32% | 55.23 |
| 13 | 山梨県 | 22.23% | 54.96 |
| 14 | 埼玉県 | 22.19% | 54.84 |
| 15 | 大分県 | 21.98% | 54.21 |
| 16 | 和歌山県 | 21.75% | 53.52 |
| 17 | 滋賀県 | 21.71% | 53.39 |
| 18 | 神奈川県 | 21.47% | 52.67 |
| 19 | 群馬県 | 21.36% | 52.34 |
| 20 | 福島県 | 21.16% | 51.74 |
| 21 | 岩手県 | 21.00% | 51.25 |
| 21 | 富山県 | 21.00% | 51.25 |
| 23 | 宮崎県 | 20.79% | 50.62 |
| 24 | 大阪府 | 20.70% | 50.35 |
| 25 | 山形県 | 20.66% | 50.23 |
| 26 | 秋田県 | 20.49% | 49.72 |
| 27 | 高知県 | 20.42% | 49.51 |
| 28 | 石川県 | 19.86% | 47.82 |
| 29 | 岡山県 | 19.44% | 46.55 |
| 30 | 佐賀県 | 19.10% | 45.53 |
| 31 | 千葉県 | 19.07% | 45.44 |
| 32 | 香川県 | 19.01% | 45.26 |
| 33 | 新潟県 | 18.69% | 44.29 |
| 34 | 愛媛県 | 18.65% | 44.17 |
| 35 | 長野県 | 18.21% | 42.84 |
| 36 | 長崎県 | 18.12% | 42.57 |
| 37 | 兵庫県 | 17.79% | 41.58 |
| 38 | 鹿児島県 | 17.73% | 41.40 |
| 39 | 鳥取県 | 17.43% | 40.49 |
| 40 | 宮城県 | 17.29% | 40.07 |
| 41 | 福岡県 | 17.07% | 39.41 |
| 42 | 京都府 | 16.31% | 37.12 |
| 43 | 島根県 | 16.24% | 36.91 |
| 44 | 広島県 | 16.19% | 36.76 |
| 45 | 奈良県 | 15.66% | 35.16 |
| 46 | 北海道 | 15.61% | 35.01 |
| 47 | 山口県 | 13.83% | 29.64 |
| 全国 | 20.27% |
□ 他との相関 相関とは?
- 赤字は本文内で言及したランキング
- [0.61] 2024年衆議院比例代表:れいわ新選組得票率 [ 2024年第一位 沖縄県 ]
- [0.60] 2022年参議院比例代表:NHK党得票率 [ 2022年第一位 沖縄県 ]
- [0.56] ハンバーグ消費量 [ 2018年第一位 沖縄県 ]
- [0.53] 産科・産婦人科医師比率 [ 2014年第一位 沖縄県 ]
- [0.51] 2021年衆議院比例代表:れいわ新選組得票率 [ 2021年第一位 沖縄県 ]
- [0.51] ひとり親世帯の相対的貧困率 [ 2018年第一位 鳥取県 ]
- [0.50] 2022年参議院比例代表:れいわ新選組得票率 [ 2022年第一位 沖縄県 ]
- ・
・ - [-0.45] 鶏肉消費量 [ 2016年第一位 山口県 ]
- [-0.46] 高校女子ソフトテニス部員数 [ 2017年第一位 岩手県 ]
- [-0.46] ワッツ・ミーツ・シルク店舗数 [ 2022年第一位 岡山県 ]
- [-0.47] 高校女子テニス部員数 [ 2017年第一位 愛媛県 ]
- [-0.47] 消費者物価地域差指数(光熱・水道) [ 2016年第一位 北海道 ]
- [-0.50] 25歳以上編み物・手芸人口 [ 2016年第一位 京都府 ]
- [-0.54] かぼちゃ消費量 [ 2016年第一位 広島県 ]
- 全ての相関を見る
□ 社会に関するその他の記事
- 2024-02-29
- 2024-01-09
- 2021-08-26
- 2021-08-26
- 2021-08-26
- 2021-04-15
- 2021-01-17
- 2021-01-17
- 2019-10-18
- 2018-07-09
- 2018-07-09
- 2018-01-11
- 2018-01-10
- 2017-12-25
- 2017-12-25
- 2017-12-25
- 2017-12-25
- 2017-12-25
- 2017-12-25
- 2017-12-25
- 2017-12-17
- 2016-08-10
- 2016-08-09
- 2016-08-08
- 2015-11-13
- 2015-06-05
- 2015-01-21
- 2015-01-21
- 2014-10-30
- 2014-01-09
- 2013-06-10
- 2013-06-04
- 2010-11-12
- 2010-11-12
- 2009-05-01
- 2009-05-01