都道府県別海苔消費量
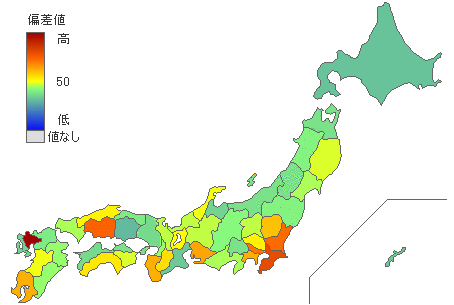
総務省の家計調査から海苔消費量の都道府県別ランキング。家計調査は全国から10000世帯を抽出して調査しており、この中から単身世帯を除いた二人以上の世帯の「干しのり」の購入量を比較している。一般世帯における購入量と消費量はほぼ同じと考えて、ここでは消費量としている。
家計調査には県庁所在地と政令指定都市の数値が掲載されており、複数の調査都市がある県はそれぞれの値を人口比で按分した数値を、それ以外の県は県庁所在地の数値を県の消費量としている。また、年による変動が考えられるので2014年~2018年の平均値をとっている。
海苔消費量の全国平均は2,601円。消費量が最も多いのは佐賀県で4,624円(偏差値89.9)。佐賀県は海苔の生産量も日本一で、海苔王国と言えそうだ。2位は千葉県で3,678円。3位以下は広島県(3,433円)、茨城県(3,374円)、東京都(3,353円)の順。一方、最も消費量が少ないのは岡山県で1,871円(偏差値37.6)。これに北海道(1,927円)、沖縄県(1,951円)、三重県(1,954円)、富山県(1,998円)と続いている。
消費量3位の広島県と、消費量最下位の岡山県が隣り合っているように、消費量が多い地域と少ない地域がちらばっていて、地域性がない。
相関ランキングでも相関係数が高いランキングが見あたらず、海苔の消費量に地域性や、他の要因との因果関係は見いだせない。
データ出典 総務省:家計調査 2018
□ 都道府県別海苔消費量
「並替」の右横の「北/南」「降順/昇順」をクリックすると並べ替え表示します。
| 順位 | 都道府県 | 消費量 | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| 並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
| 1 | 佐賀県 | 4,624円 | 89.89 |
| 2 | 千葉県 | 3,678円 | 71.92 |
| 3 | 広島県 | 3,433円 | 67.27 |
| 4 | 茨城県 | 3,374円 | 66.15 |
| 5 | 東京都 | 3,353円 | 65.75 |
| 6 | 愛知県 | 3,083円 | 60.62 |
| 7 | 和歌山県 | 3,019円 | 59.41 |
| 8 | 神奈川県 | 3,005円 | 59.14 |
| 9 | 鹿児島県 | 2,999円 | 59.03 |
| 10 | 栃木県 | 2,944円 | 57.98 |
| 11 | 奈良県 | 2,741円 | 54.13 |
| 12 | 高知県 | 2,700円 | 53.35 |
| 13 | 島根県 | 2,654円 | 52.47 |
| 14 | 埼玉県 | 2,649円 | 52.38 |
| 15 | 滋賀県 | 2,610円 | 51.64 |
| 16 | 石川県 | 2,547円 | 50.44 |
| 17 | 熊本県 | 2,541円 | 50.33 |
| 18 | 岩手県 | 2,500円 | 49.55 |
| 19 | 徳島県 | 2,473円 | 49.03 |
| 20 | 福井県 | 2,470円 | 48.98 |
| 21 | 群馬県 | 2,454円 | 48.67 |
| 22 | 京都府 | 2,439円 | 48.39 |
| 23 | 岐阜県 | 2,427円 | 48.16 |
| 24 | 宮城県 | 2,407円 | 47.78 |
| 25 | 静岡県 | 2,390円 | 47.46 |
| 26 | 山口県 | 2,382円 | 47.31 |
| 27 | 大分県 | 2,353円 | 46.75 |
| 28 | 宮崎県 | 2,337円 | 46.45 |
| 29 | 大阪府 | 2,318円 | 46.09 |
| 30 | 長野県 | 2,303円 | 45.80 |
| 31 | 秋田県 | 2,245円 | 44.70 |
| 32 | 福島県 | 2,209円 | 44.02 |
| 33 | 福岡県 | 2,203円 | 43.91 |
| 34 | 鳥取県 | 2,199円 | 43.83 |
| 35 | 新潟県 | 2,153円 | 42.96 |
| 36 | 山梨県 | 2,149円 | 42.88 |
| 37 | 山形県 | 2,132円 | 42.56 |
| 38 | 香川県 | 2,117円 | 42.27 |
| 39 | 青森県 | 2,112円 | 42.18 |
| 40 | 愛媛県 | 2,091円 | 41.78 |
| 41 | 兵庫県 | 2,088円 | 41.72 |
| 42 | 長崎県 | 2,015円 | 40.33 |
| 43 | 富山県 | 1,998円 | 40.01 |
| 44 | 三重県 | 1,954円 | 39.18 |
| 45 | 沖縄県 | 1,951円 | 39.12 |
| 46 | 北海道 | 1,927円 | 38.66 |
| 47 | 岡山県 | 1,871円 | 37.60 |
| 全国 | 2,601円 |
□ 他との相関 相関とは?
- 赤字は本文内で言及したランキング
- [0.46] 羊羹消費量 [ 2018年第一位 佐賀県 ]
- [0.46] 女性医師比率 [ 2014年第一位 東京都 ]
- [0.44] しゅうまい消費量 [ 2018年第一位 神奈川県 ]
- [0.44] プロ野球野手出身地 [ 2009年第一位 佐賀県 ]
- [0.44] 在日スリランカ人 [ 2018年第一位 茨城県 ]
- [0.43] 年間快晴日数 [ 2020年第一位 埼玉県 ]
- [0.42] 外食費用 [ 2016年第一位 東京都 ]
- ・
・ - [-0.41] 鉄道旅客域内移動率 [ 2013年第一位 沖縄県 ]
- [-0.43] オートバックス店舗数 [ 2009年第一位 富山県 ]
- 全ての相関を見る
□ 食生活に関するその他の記事
- 2020-11-18
- 2020-11-18
- 2020-07-09
- 2020-07-09
- 2020-07-09
- 2020-07-09
- 2020-07-09
- 2020-07-09
- 2020-05-28
- 2020-05-28
- 2020-05-20
- 2020-05-20
- 2020-05-20
- 2020-05-19
- 2020-05-19
- 2020-05-19
- 2020-04-09
- 2020-04-09
- 2020-04-09
- 2020-04-08
- 2020-04-08
- 2020-02-07
- 2020-02-06
- 2020-01-17
- 2020-01-17
- 2020-01-16
- 2020-01-16
- 2020-01-16
- 2020-01-16
- 2020-01-16
- 2020-01-09
- 2020-01-09
- 2020-01-09
- 2020-01-09
- 2020-01-08
- 2020-01-08
- 2020-01-08
- 2020-01-07
- 2020-01-07
- 2020-01-07
- 2020-01-07
- 2020-01-07
- 2020-01-07
- 2020-01-06
- 2020-01-06
- 2019-12-13
- 2019-12-13
- 2019-12-13
- 2019-12-13
- 2019-12-13
- 2019-12-13
- 2019-12-13
- 2019-12-13
- 2019-12-13
- 2019-12-13
- 2019-12-13
- 2019-12-13
- 2019-12-12
- 2019-12-12
- 2019-12-12
- 2019-12-12
- 2019-12-12
- 2019-12-12
- 2019-12-12
- 2019-12-11
- 2019-12-11
- 2018-01-31
- 2017-12-12
- 2017-12-12
- 2017-11-15
- 2017-11-14
- 2017-11-14
- 2017-11-13
- 2017-09-08
- 2017-08-24
- 2017-08-22
- 2017-08-22
- 2017-08-22
- 2017-08-22
- 2017-08-09
- 2017-08-09
- 2017-08-09
- 2017-08-04
- 2017-08-01
- 2017-08-01
- 2017-08-01
- 2017-07-28
- 2017-07-28
- 2017-07-27
- 2017-07-27
- 2017-07-26
- 2017-07-26
- 2017-07-14
- 2017-07-14
- 2017-07-14
- 2017-07-13
- 2017-07-13
- 2017-07-12
- 2017-07-12
- 2017-07-11
- 2017-07-11
- 2017-07-11
- 2017-07-10
- 2017-07-07
- 2017-06-10
- 2017-06-06
- 2017-06-01
- 2017-06-01
- 2017-06-01
- 2017-05-29
- 2017-05-29
- 2017-05-29
- 2017-05-24
- 2017-05-24
- 2017-05-23
- 2017-05-22
- 2017-05-17
- 2017-05-15
- 2017-05-11
- 2017-05-11
- 2017-05-11
- 2017-05-11
- 2017-05-09
- 2017-05-02
- 2017-05-02
- 2017-05-02
- 2017-04-27
- 2017-04-24
- 2017-04-24
- 2017-04-12
- 2017-04-11
- 2017-04-11
- 2017-04-07
- 2017-04-05
- 2017-04-02
- 2017-03-29
- 2017-03-29
- 2015-08-21
- 2015-08-20
- 2015-08-20
- 2015-08-19
- 2014-07-30
- 2014-07-25
- 2014-07-23
- 2014-06-12
- 2014-06-10
- 2014-06-10
- 2014-06-10
- 2013-07-16
- 2013-07-12
- 2013-07-04
- 2013-07-03
- 2013-06-13
- 2013-06-11
□ 消費量の分布 (変動係数 0.2086)
□ この記事を見た人はこちらも見ています
□ コメント
はちお 2012/12/28
広島県民です。
この結果は納得の結果ですね。
実は日本で二番目に海苔養殖を開始したのが広島藩で、その後も、長く江戸と広島でのみ養殖されていました。
その時代根付いた食生活が現代まで残っているのだと思います。
分布を見る限り、有明海を擁する佐賀県など養殖が盛んな土地ほど消費量も増える傾向があるように思われます。
この結果は納得の結果ですね。
実は日本で二番目に海苔養殖を開始したのが広島藩で、その後も、長く江戸と広島でのみ養殖されていました。
その時代根付いた食生活が現代まで残っているのだと思います。
分布を見る限り、有明海を擁する佐賀県など養殖が盛んな土地ほど消費量も増える傾向があるように思われます。
かいもん 2012/08/30
さすが有明海のお膝元佐賀県。隣の諫早湾堤防を判決に背いてあけようとしないN県は42位。N件県民にとっては有明湾の海苔がどうなろうと関係なく、公共工事で得た干拓地を手放したくないことがはっきりと分かる結果。いずれ強制執行されるだろうけど。
もともとの生産地でそれを土台にした食文化のある地域なのが如実に出てるじゃない。分からない?
ランキング5位までは近世から近代、現代に至るまでの生産地だよ。
東京湾とか昔は海苔の産地だったのにそんなことも知らないのかよ。